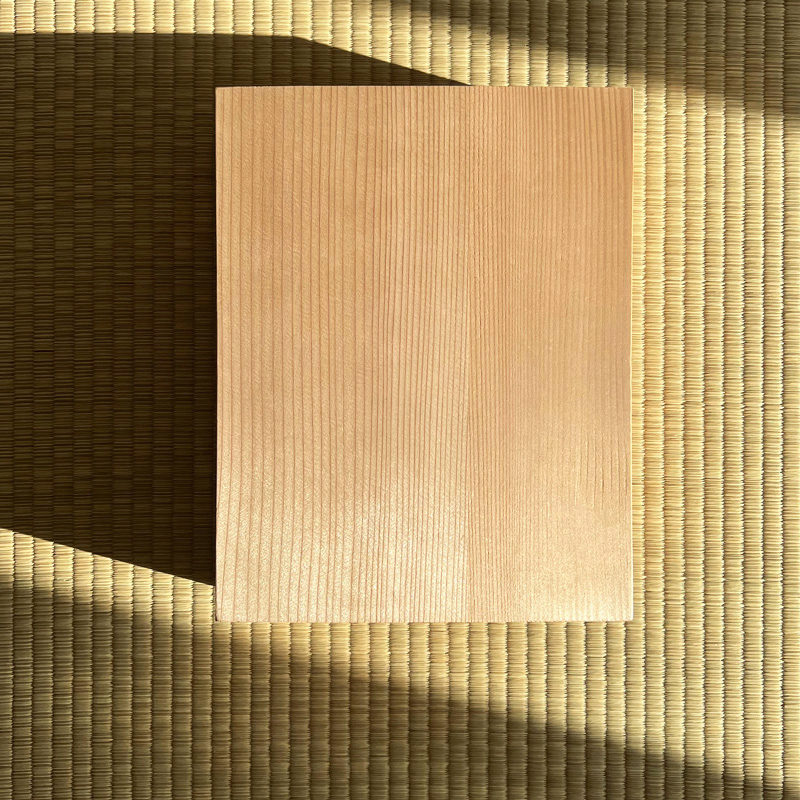#23
well-being / keeping / recycling
古民家したさん
小さな地球
Kamogawa, Chiba, Japan
the product:
古民家「したさん」は、千葉県鴨川市の山間部、25世帯ほどの釜沼集落にあります。 豊かな里山と雨の恵みだけで育つ天水棚田を有し、日本の原風景が残る美しい土地です。もともとは大正時代に村長をつとめた方の家で、敷地内には蔵や牛小屋があり、裏手には竹林、目の前には水田が広がっています。
代々住み継がれてきた古民家でしたが、2019年の大型台風15号で被災。同時期に里山つきで売りにだされます。釜沼集落に移住後、棚田の保全などに取り組んでいた林良樹さんは、一般社団法人「小さな地球」を立ち上げ、古民家の共同購入を決意します。
この集落で呼び合っていた村長さんの屋号の「したさん」をそのまま残して、古民家したさんと名付け、人が集う村長さんの家の風格はそのままに、コミュニティスペースとして新しく生まれ変わりました。 宿泊をはじめ、カフェ、企業や大学の研修、オーガニック・マーケットなどのイベントや、多様な人たちが集う場所として活用されています。
2021年からはじまった古民家のリノベーション。 改修には東京工業大学塚本研究室の学生たちと共に、解体や設計など各種工事を自分たちの手で行いました。
古民家の魅力は最大限に残しつつ、できるだけゴミを出さないように、使える材料を再利用できるように丁寧に解体。また、足りないものは、できるだけ集落にあるものを利用して、現在もすこしづつ改修を行っています。
・壁、床
土壁の土は、棚田に排水用の溝を掘った際に出た土を利用し、土壁の下地には、裏山の竹林からとってきた竹を細い格子状に編み込んだものを入れています。
塗り重ねて仕上げた土壁は、そのまま残した昔の電話機や電気の配線などと調和しています。
・土間
広い土間だったところは、もともとあった土を取り除き、土の中の環境改善のために竹杭を打ち込み、炭と藁を入れたコンクリート仕上げに。そこに、新しくカウンター型の大きなコミュニティキッチンと薪ストーブをつくり、みんなが集まれるラウンジスペースとなりました。
ラウンジのランプシェードには、壁の下地と同じく、裏山でとってきた竹を細かく編んだものが使われています。
・お風呂
増築したお風呂は、大きな窓が裏山に面した解放感のあるつくり。外壁には、獣害対策の際に伐採した、杉の木の皮を剥いだものが再利用されています。
窓辺に置かれたまるい信楽焼の風呂釜は、熱を程よく蓄熱し体があたたまります。
・屋外
水田の前には広い焚き火スペース、母屋に隣接した屋根付きのBBQスペースがあるので、天候問わず楽しむことができます。
牛小屋だったところは物置、蔵はギャラリーになっています。
時がたった古民家「したさん」に、改修の際に加わった機能的な設備は、昔からあったかのように馴染んでいます。
現在でも、少しずつ建物とまわりの環境が循環して調和できるように改修手入れは少しずつ続いています。
(...)
(-)
the maker:
古民家「したさん」と同じ釜沼集落にある古民家「ゆうぎつか」に暮らす林良樹さん。林さんは、自然とアートとを追求しながらアメリカ・アジア・ヨーロッパなど世界各地を回り、天水棚田、炭焼き小屋、みかん畑、茅葺の古民家など、日本の原風景が残る美しい農村に一目惚れして、1999年に移住しました。 以来、高齢化が進んでいたこの集落で「美しい村が美しい地球を創る」をテーマに、釜沼北棚田オーナー制度、無印良品 鴨川里山トラスト、天水棚田でつくる自然酒の会、釜沼木炭生産組合、地域通貨あわマネー、大学や企業の研修など、人と人、人と自然、都会と田舎をつなぐ多様な活動を主宰し、その活動全体を「いのちの彫刻」としています。
2019年台風15号被災後、一般社団法人小さな地球を設立し、古民家や棚田を含む里山全体を社会の共有財産(コモンズ)とする活動を始めました。
・地域通貨あわマネー
2002年に、千葉県南部、安房(あわ)地域で使えるコミュニティの地域通貨「あわマネー」を導入します。
1awa=1円を目安に、お金のように、物々交換のように使うことができる通帳で、地域に暮らす人々が、自分たちのできる方法で助け合える仕組みになっています。
・釜沼北棚田オーナー制度
2006年より、都市に住む人たちに棚田のオーナーになってもらい、高齢化で管理ができなくなった棚田に毎月通って稲作を行い保全する活動を行っています。
この活動によって、地元住民、移住した住民と都市に住む人たちが繋がり、都会と田舎を超えたコミュニティが育まれています。
・NPO法人うず
林さんが運営する「NPO法人うず」は2014年から無印良品くらしの良品研究所と「鴨川里山トラスト」という活動を行っています。活動は天水棚田でのお米づくりの他、稲刈りをした稲わらでしめ縄飾りをつくるなど、日本の食文化や手仕事を通して、里山を保全することを目的としています。
また、無印良品は新しい働き方のシンボルとして、鴨川里山トラストで保全している天水棚田の真上に棚田オフィスを建設しました。設計は建築家の塚本由晴さん(アトリエ・ワン/東京工業大学教授)です。
・茅葺き再生
2019年の秋、釜沼集落に台風15号が直撃し、林さんが暮らす古民家「ゆうぎつか」の茅葺き屋根にかけてあるトタン板がすべて吹き飛んでしまいます。林さんは、トタン板で覆われて隠れていた茅葺き屋根の美しさに魅了されて、茅葺きの屋根を元に戻すことに決めます。
かつて釜沼集落には、材料の茅を育てる共有の茅場もあり、毎年、新しい茅を集落の家に順番に葺き替え、地域で循環していました。しかし、過疎化が進み、茅場も共有地も共同作業もなくなったことで、茅葺き屋根は維持できなくなり、今ではとても高価なものになってしまいました。林さんは、まずは茅葺屋根の材料のススキを育てるため、耕作放棄地を開墾して茅場をつくることからはじめます。
茅葺きの再生には「新しい結」をつくり、毎年茅葺き合宿を行い、職人から知識や技術を学び、茅葺きスクールのように茅葺き屋根を葺き替えています。
・一般社団法人小さな地球
2019年、台風で被災した自宅の復旧作業が続くなか、同じく被災した古民家「したさん」が同時期に売りに出されます。林さんは、一世代で絶えることなく、しっかりと未来に繋げていくために、共同購入することを考えます。林さんのこれまでの活動に共感する方々に出資を募り、古民家「したさん」の共同購入と運営をきっかけに、「一般社団法人小さな地球」を設立します。
「小さな地球」では、古民家「したさん」をはじめ、冬場の草刈り、耕作放棄地の開墾、獣害対策の電柵周りの伐採など、里山の環境整備を都市に暮らす人たちとしています。
ときには、大工や造園家などの様々な専門家によるレクチャーや、ワークショップをひらき、戸や窓の調整、土中環境の改善や、茅葺きなど、さまざまな知識や技術を多くの人と共有し、暮らしや社会を持続可能に循環できるような取り組みを行っています。
自然と伝統の文化や知恵、現代文明の良い部分を合せて、人と自然が豊かに繋がる新しい文化を次世代へ伝えています。
1千年続く棚田と古民家を含む里山の再生をきっかけに、いまでは、都市に住むひとたちや企業、大学、NPOまで広がり、釜沼の里山は地縁血縁を超えた「みんなのふるさと」となっています。
small-earth.org
(...)
(-)
#25
cooking / eating
無水鍋®
HALムスイ
HIROSHIMA, hiroshima, Japan
- aluminium
- 20: W27.4cm H11.2cm inside ø20cm 24: W31.6cm H14.3cm inside ø24cm
the product:
水を加えることなく調理ができる、無水鍋®。素材に含まれている水分や油分を活かすことで、豊かな風味や濃厚な味わいを引き出し、栄養を逃さず美味しく仕上げます。
鍋と蓋は、鋳物ならではの厚みがありながら、軽量で丈夫なつくり。密閉度が高く、蒸気を逃がさず無水調理を行うことができます。
また、アルミニウムの特長である優れた熱効率で、弱火でも鍋全体にあっという間に、ムラなく均一に熱が伝わります。保温力にも優れているため、余熱調理も可能です。
基本の無水調理は、中火弱で2分程度(天火調理は5分)予熱し、鍋が十分に温まったら水滴を落とします。その水滴が玉になってコロコロと転がったら適温のサインです。強火で一気に加熱せず、中火弱の火加減でじっくりあたためるのがポイントです。鍋を予熱することで、食材が鍋にくっつきにくくなるという利点があります。
無水鍋®をアウトドアで使用するのもおすすめ。フラットな蓋の上に炭を置けば、上下から加熱することもできます。
また、蓋はひっくり返してフライパンとしても使えます。たとえば、蓋をフライパンとして使用し、その上に鍋を被せれば、鶏丸ごと1羽の蒸し焼きも簡単に。
蓋の部分で炒め物をして、温かいスープが入った鍋の上にスタッキングすれば、鍋の蓋としての機能を果たしつつ、炒め物をスープの熱で保温することができます。
無水鍋®ひとつで、鍋、蓋、フライパン、蒸し器としても使えるので、さまざまな調理器具を持ち運ぶ必要がなく、とても便利です。
調理後は、塩分や水分で金属部分が傷むことがあるため、鍋の中に料理を入れたままにせず、別容器で保存するようにします。
長く使うことで、鍋の黒ずみが起こる場合がありますが人体に影響はありません。
お手入れは、十分に冷ましてから中性洗剤で洗います。中性洗剤で落ちない場合は、スチールタワシにクレンザーを適量とり、円を描くように磨きます。
塗装されていない、アルミニウムの素材をそのままを生かした無水鍋®は、傷がついても目立ちにくく、使い込むほどに味が出て「自分だけの鍋」という魅力が増します。
「グッドデザイン賞」「グッドデザイン・ロングライフデザイン賞」受賞。
販売中のKING無水鍋🄬は、ガスとIH対応、蓋は直火専用。
内径18cm、20cm、24cmの3サイズ展開。
※写真は、ガス専用無水鍋®で、取っ手に「KING」の刻印のない旧モデルの24cmになります。現在、数量限定・特別販売されています。
(...)
(-)
the maker:
1921年創業の田島倉造商店。その歴史は、アルミニウム製の羽釜をの製造・販売から始まりました。軽くて火がよく通る羽釜は、当時の台所の熱源だったかまどと相性が良く人気を博します。
1946年頃、ガスの普及により台所の熱源はかまどからガスコンロへと移行。 1947年、広島アルミニウム工業有限会社設立。
1950年、田島倉造商店を(株)田島商店に名称変更。
事業の2本柱である製造業は広島アルミニウム工業、卸業は田島商店と、分業体制になります。
1953年、世界有数と評されるまでに成長した鋳造・加工技術で、ガスでも羽釜と同じくらい美味しいご飯が炊ける「無水栄養ナベ」を開発します。
ご飯がおいしく炊けるほかに、煮る、 茹でる、焼く、蒸す、炒める、揚げる、オーブン調理ができる1鍋8役の優れもの。食材の旨みを短い時間で引き出す無水鍋®は、累計1000万台を販売するロングセラー商品となります。
その後、アルミニウム製品の砂型鋳造技術が評価され、自動車部品産業に参入。
1963年、「無水鍋®」の商標が正式登録されます。
さらに時は流れ、かまどからガス、IHへと熱源の選択肢が増え、家族のかたちも大家族から核家族へと変化していきます。確かな技術で、ガスとIH両方に対応できる製品の開発や、ひとまわり小さいサイズのラインナップを充実させるなど、時代の変化に合わせた商品を展開しています。
2018年 製造元である広島アルニウム工業株式会社の、広島の「H」と、アルミニウムの「AL」を組み合わせて、販売元「株式会社 HALムスイ」を設立します。
大正、昭和、平成、令和にわたり愛されてきた無水鍋®を「KING」シリーズ、デザインと機能の向上させた「HAL」シリーズと名づけ、多様化するライフスタイルに寄り添いつづけます。
これらの鍋は、開発された当初から変わらず、広島の地で、職人による鋳造技術で丁寧につくられています。
(...)
(-)
#10
lighting / wrapping / keeping
ミツロウ
Everywhere
ミツロウとは
ミツロウは、花粉などとミツバチの体内で混ぜ合わせて分泌した蝋でできた六角形の巣を精製したものをいいます。未精製で漂白していない成分が残っている黄色いミツロウと、漂白した香りのない白いミツロウの2種類があります。黄色いミツロウは、採れる地域やミツバチ、ミツバチが集めた花の種類や花粉の量で、薄い黄色から濃いオレンジ、茶色と変わります。ほのかに甘い匂いがして、少しべったりした手触りです。
抗菌性と耐水性に優れていて、ろうそく、クレヨン、家具のワックス、革用のクリーム、バームなど、用途もさまざま。食用としても、型にミツロウを塗って焼くカヌレや、チョコレートや飴のコーティングなどにも使われているそうです。
抗菌性と耐水性に優れていて、ろうそく、クレヨン、家具のワックス、革用のクリーム、バームなど、用途もさまざま。食用としても、型にミツロウを塗って焼くカヌレや、チョコレートや飴のコーティングなどにも使われているそうです。
ミツロウ テーパーキャンドル
ミツロウは、一般的なロウソクの材料のパラフィンと比べて、融点が約62℃〜65℃と高くゆっくりと燃焼するため、すすがでにくいのが特徴です。
ヨーロッパの伝統的なディッピング式のテーパーキャンドルは、型がなくてもタコ糸があればキャンドルを作ることができます。タコ糸の真ん中を持って紐の両端を溶かしたミツロウにつけて、乾かす作業を繰り返してつくります。途中、芯をまっすぐになるように形を整えて、好きな太さになったら、吊るして固めます。
1本のタコ糸につながった2本のキャンドルは、ミツロウを同時にディッピング、乾燥ができて、使うときにはタコ糸を切って火を灯すという、全ての工程にタコ糸が存分にいかされています。ミツロウが垂れながら乾いた、重力を感じられる少し下ぶくれの美しいフォルム。
ミツロウキャンドルが灯すあたたかいオレンジ色のあかりと、ほのかに漂う甘い香りで穏やかな気分になります。
石油由来のパラフィン、ガスや電気のなかった時代に使われていたミツロウキャンドル。ミツバチによってつくられたミツロウキャンドルを灯すと、改めて自然と電気のありがたみを感じることができます。
ヨーロッパの伝統的なディッピング式のテーパーキャンドルは、型がなくてもタコ糸があればキャンドルを作ることができます。タコ糸の真ん中を持って紐の両端を溶かしたミツロウにつけて、乾かす作業を繰り返してつくります。途中、芯をまっすぐになるように形を整えて、好きな太さになったら、吊るして固めます。
1本のタコ糸につながった2本のキャンドルは、ミツロウを同時にディッピング、乾燥ができて、使うときにはタコ糸を切って火を灯すという、全ての工程にタコ糸が存分にいかされています。ミツロウが垂れながら乾いた、重力を感じられる少し下ぶくれの美しいフォルム。
ミツロウキャンドルが灯すあたたかいオレンジ色のあかりと、ほのかに漂う甘い香りで穏やかな気分になります。
石油由来のパラフィン、ガスや電気のなかった時代に使われていたミツロウキャンドル。ミツバチによってつくられたミツロウキャンドルを灯すと、改めて自然と電気のありがたみを感じることができます。
ビーズワックスラップ
布にミツロウを染み込ませた、ビーズワックスラップ。
乾燥しないようにパンやおにぎりを包んだり、お皿や容器に蓋をしたり、折り紙のように袋の形に折ってスナックをいれるなど、自由な形にできてとても便利です。包む時に、手のぬくもりでしっかりとおさえることで、、少しべたっとしたビーズワックスペーパーが柔らかくなりピタッとくっつきます。
ミツロウの抗菌・保湿効果で、鮮度を保てるのでフードロスの削減にも。
水洗いして、何度でも繰り返し半年から1年くらい使えます。使い終わったビーズワックスラップは、土にもどるので環境にも優しいです。
作りたいサイズの布と、ミツロウとアイロン、クッキングペーパーがあれば、簡単に作ることができます。
乾燥しないようにパンやおにぎりを包んだり、お皿や容器に蓋をしたり、折り紙のように袋の形に折ってスナックをいれるなど、自由な形にできてとても便利です。包む時に、手のぬくもりでしっかりとおさえることで、、少しべたっとしたビーズワックスペーパーが柔らかくなりピタッとくっつきます。
ミツロウの抗菌・保湿効果で、鮮度を保てるのでフードロスの削減にも。
水洗いして、何度でも繰り返し半年から1年くらい使えます。使い終わったビーズワックスラップは、土にもどるので環境にも優しいです。
作りたいサイズの布と、ミツロウとアイロン、クッキングペーパーがあれば、簡単に作ることができます。
(...)
(-)